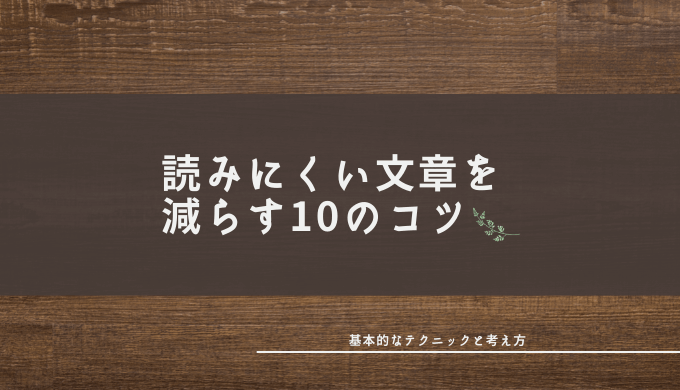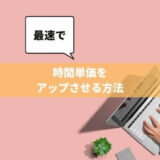Webライターとして稼ぐには読みやすい文章を書く必要があります。
ただし「読みやすい文章」というのは非常に難しいテーマです。
なぜなら読む相手がさまざまなので、人によって読みやすい文章は違います。
ですが、すべての人にとって読みにくい文章というのは存在します。
この記事では、読みにくい文章を書かないために気をつける10のコツをご紹介しています。
- PREP法をマスターする
- 改行に気をつける
- 漢字とひらがなのバランスを考える
- 文末が続かないように注意する
- 順接の「が」に注意する
- 「することができる」を多用しない
- 思いますを使わない
- こそあどは使わない
- 重複表現がないかチェックする
- 時間を空けて推敲(すいこう)する
実践することで1段階レベルの上がった文章が書けるようになるでしょう。
ぜひ参考にしてください。
目次
PREP法をマスターする

PREP法は結論を最初に書くテクニックです。
結論を最初に書くので理解しやすい文章になります。
初心者WebライターはまずはPREP法を覚えることから始めてください。
PREP法を使えば、誰でも簡単に理解しやすい文章が書けます。
関連記事Webライターがまず学ぶべきPREP(プレップ)法とは
改行に気をつける
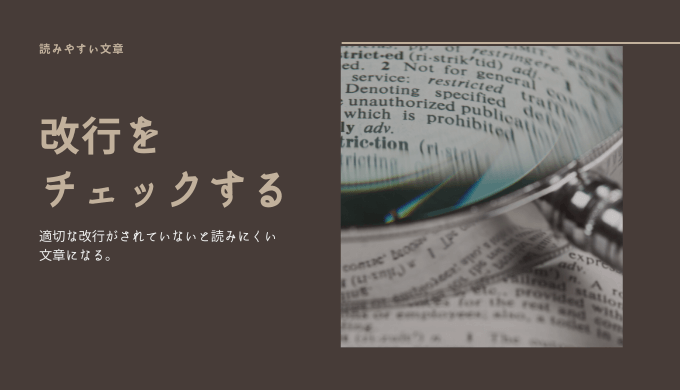
適切に改行がされていないと読みにくい文章になります。
適度な改行がないと文字が詰まって読む気が失せるからです。
基本は読点(。)が来たら改行してください。
ただし、文章が短すぎる時は2つの文章をつなげた方が読みやすい文章もあります。
慣れてきたら、あえて続けるテクニックも使ってみてください。
とりあえず初心者のうちはまずは読点(。)で改行する意識を持っていればOKです。
漢字とひらがなのバランスを考える

漢字を使うことを「文字を閉じる」、ひらがなを使うことを「文字を開く」と呼びます。
漢字が多過ぎると読みにくいし、ひらがなばかりだと幼稚な印象を受けるのでバランスが大切です。
なお、Webの文章ではひらがなを使うことが鉄則になっているものもあります。
- 出来る → できる
- 事 → こと
- 有難い → ありがたい
- 及び → および
- 何処 → どこ
パソコンで打っていると簡単に変換できるのでつい漢字を使ってしまいがちです。
漢字を使うかどうか迷ったら、記者ハンドブックを参考にすると良いでしょう。
ひらがなを使った方がいいのか漢字を使った方がいいのか、すぐに調べられます。
Webライターならぜひ持っておきたい1冊です。
文末が続かないように注意する
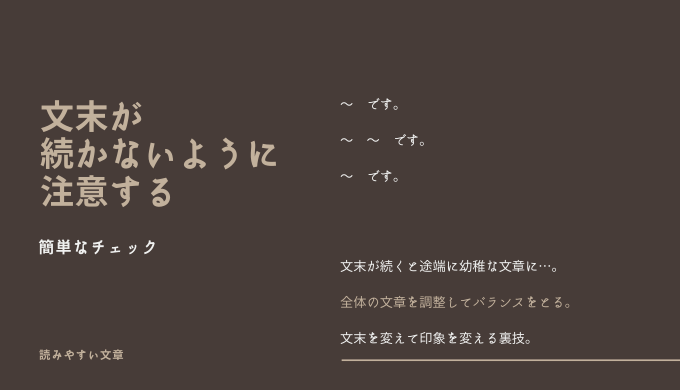
文末が続くと途端に幼稚な文章になってしまいます。
例えば以下のような文章です。
Webライターを始めようと思っています。
今はブログで勉強しています。
今度クラウドワークスで応募してみます。
文末を変えるだけで印象は変わります。
Webライターを始めることにしました。
今はブログで勉強しています。
今度クラウドワークスで応募する予定です。
文末が2つ続いたら注意し、3つ続いたらアウトです。
続かないようにするため文末を変えて、日本語がおかしくなってしまったら意味がないので全体の文章を調整してバランスをとってください。
簡単に文末を変える裏技があります。
それは体言止めを使うことです。
例えば、先程のわかりにくい文章の真ん中を体言止めにしてみます。
Webライターを始めようと思っています。
今はブログで勉強中。
今度クラウドワークスで応募してみます。
これで文末が続くよりは良い文章になりました。
体言止めは使い過ぎると高圧的な文章になってしまいますので、ほどほどに利用してください。
順接の「が」に注意する
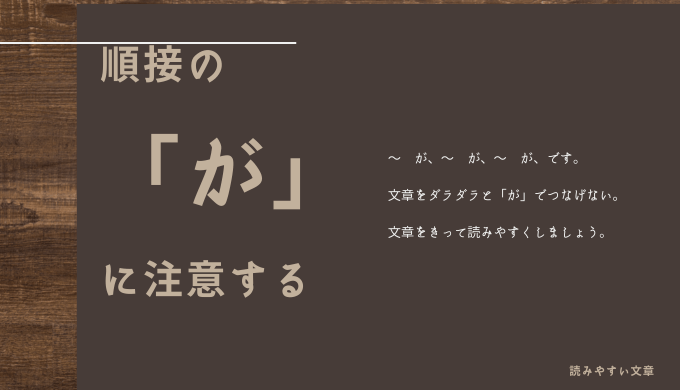
順接の「が」とは、文章をダラダラと「が」でつなげてしまうことです。
例えば、こんな文章が該当します。
先日お伝えした件ですが、お客様からOKの回答はもらったのですが、これから着手して良いでしょうか?
とても読みにくいですね。
この場合は、単純に文章を切れば読みやすくなります。
先日お伝えした件です。
お客様からOKの回答をもらいました。
これから着手して良いでしょうか?
「が」が入ると「なにか想定外のことが起こったのだろうか?」と気になり理解しにくくなります。
メールやチャットでもやりがちなので注意してください。
することができるを多用していないか
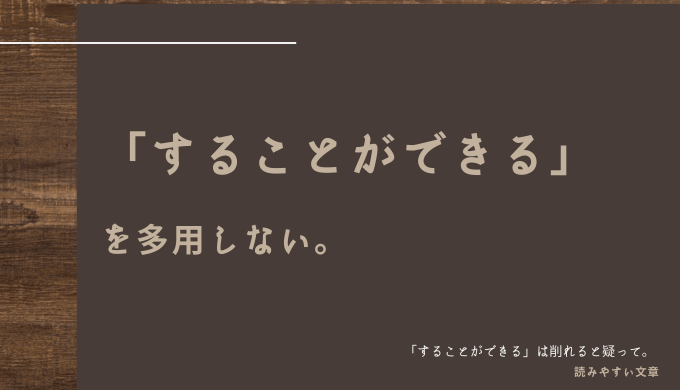
「~することができる」は削れる場合が多いのでチェックしましょう。
- 食べることができる → 食べられる
- 見ることができる → 見られる
- 教えることができる → 教えられる
「~ことができる」を見つけらた削っても問題ないのでは?と疑ってください。
思いますを使わない
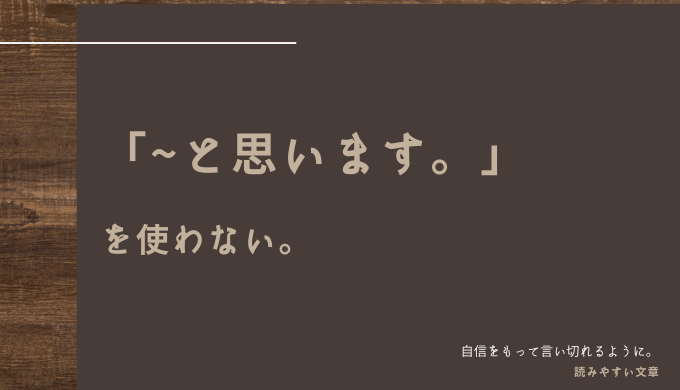
「〜思います。」は自分の意見なのでライターが使うのはNGです。
使ってOKの場合もありますが、原則NGなので「思います」は使わないと覚えておいてください。
また、文章を書いていると言い切る自信がなく「~と思います。」と書いてしまいがちです。
読者には自信のなさが10倍以上にもなって伝わるので思い切って言い切りましょう。
言い切れない時はインプットや確証が足りない時です。
リサーチをしっかりして、自信を持って言い切れるようにしてください。
こそあどは使わない
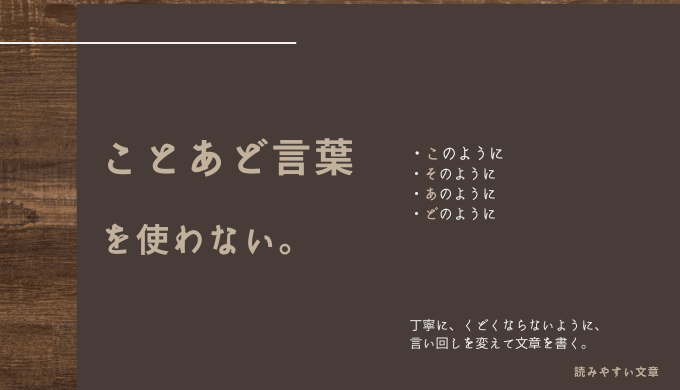
こそあど言葉とは以下のようなものです。
- このように
- そのように
- あのように
- どのように
Webの文章は基本的に全て読まれないものと覚えてください。
読者は読み飛ばして気になったところだけ読むからです。
ですので、文章の途中で「このように」と出てきても「どのように?」となり理解できなくなってしまいます。
前に書いてあるからとか、もうわかるだろうという文章はNGで、丁寧に、そして くどくならないように言い回しを変えて文章を書くようにしてみてください。
例えば次のような書き方です。
実力を提示できるポートフォリオがあると応募するときに有利です。
クライアントに今の実力を見せて安心させましょう。
このようにすると採用率がアップします。
赤字の部分を違う言い回しで具体的に書きます。
実力を提示できるポートフォリオがあると応募するときに有利です。
クライアントに今の実力を見せて安心させましょう。
自身でブログを運営し実績として提示すると採用率がアップします。
意識してみましょう。
重複表現がないかチェックする
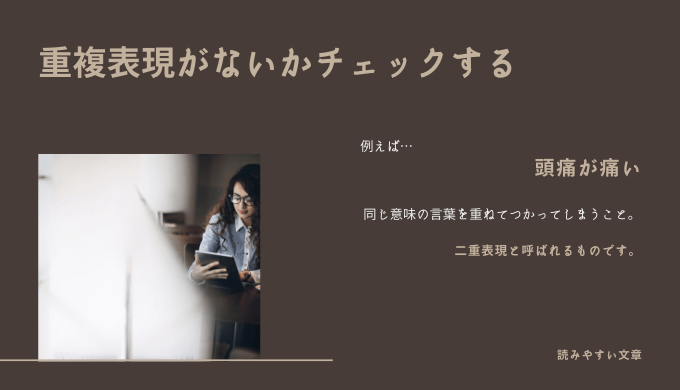
重複表現とは同じ意味の言葉を重ねて使ってしまうことです。
二重表現と呼ばれることもあります。
例えば以下のようなものです。
- 一番最初 → 一番初め
- 返事を返す → 返事をする
- 後で後悔するなら → 後悔するなら
意識しないと自然に使ってしまうことが多いので注意してください。
時間を空けて推敲(すいこう)する
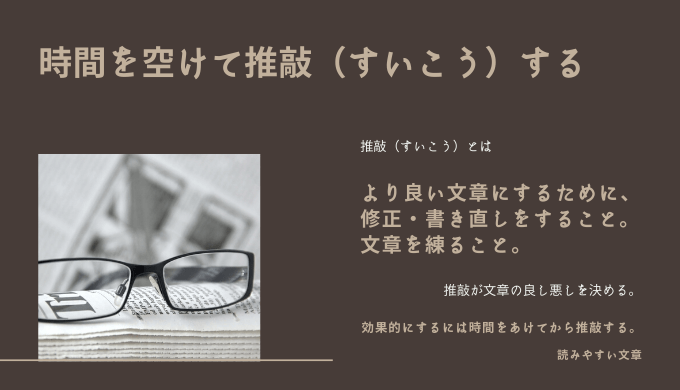
推敲とは、より良い文章にするため修正したり書き直したりすることです。
この推敲が文章の良し悪しを決めるといっても過言ではありません。
推敲を効果的に行うには時間をあけるのが有効です。
時間をあけると客観的な視点を持って文章を見られるので、わかりにくい部分や改善するべき点が見つけやすくなります。
文章を書き上げたら一晩眠ってから改めて文章を見返してください。
前日には完璧だと思っていた文章から、改善点がたくさん見つかります。
ぜひ試してみてください。
まとめ:読みにくい文章を減らして読みやすい文章の下地を作ろう
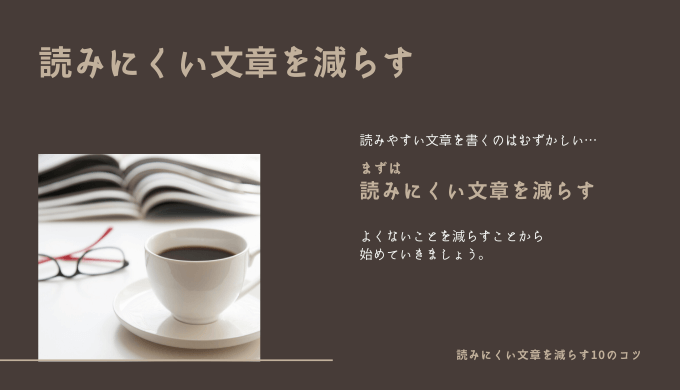
読みやすい文章を書くのは非常に難しいことです。
人によって読みやすいと感じる文章は違います。
まずは読みにくい文章を減らすことから始めてみましょう。
- PREP法をマスターする
- 改行に気をつける
- 漢字とひらがなのバランスを考える
- 文末が続かないように注意する
- 順接の「が」に注意する
- 「することができる」を多用しない
- 思いますを使わない
- こそあどは使わない
- 重複表現がないかチェックする
- 時間を空けて推敲(すいこう)する
これらに注意してみてください。
読みにくい文章が減れば、確実に読みやすい文章に近づきます。